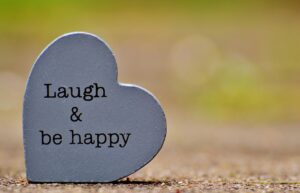今は多種多様な習い事があって驚く。
かけっこ教室というのをテレビでみて、もし子供の頃あったら行きたかったなぁ、と鈍足の私は思う。
なんでもそうだが、昭和の昔は選択肢が少なかった。
習い事は、たまたま近所にあった書道教室やそろばんに行ってみる、みたいに選び方もかなり適当だった気がする。
今はネットで調べて、わざわざ良い教室に遠くから通ったり、習いたいものがあれば、かなり珍しいものでも教室を見つけることができる。
ご両親が共働きだから、学童保育の代わりに毎日習い事に行っている、なんて子もいるらしい。
お月謝
習い事はビギナーには優しい。
最初は始めやすいように、お月謝が安く設定されている。
「お友達がやっているからやりたい」と子供に言われたら、払えなくはない金額だと、よく考えずに何となく始めてしまったりする。
何年か経つと上手くなってきて、次のランクに上がり、お月謝も上がっていく。
親は我が子が上達したのが嬉しいので、喜んで払う。
でももうしばらくすると、、ここからが親の悩みどころだ。
このまま続けていいのか?
塾に行かせた方がいいのではないか?
塾などの教育費は高い。
できれば最も効果的な使い方がしたい。
習い事と子供の将来
私はピアノが好きだ。
子供の頃習っていたが、経済的理由で小5で辞めた。
そして10年ほど前に、ピアノを再開した。
今はこのオンラインレッスンを受けながら、日々楽しんでいる。
ちょっと前になるが、前回のショパンコンクールの時は、毎日YouTubeで聴いてワクワクしていた。
反田恭平さんが2位、小林愛実さんが4位と、素晴らしい結果だった。
ご両親はさぞかしお喜びだろうと、親目線で考えてしまう。
かなり以前に記事で読んだのだが、小林愛実さんは山口県出身で、ご両親は音楽関係ではないそうだ。
愛実さんのピアノの才能が素晴らしく、有名な先生のレッスンを受けるために小学校低学年の時から度々東京に来ていたらしい。
そしてついにお父さんがお仕事を辞めて、愛実さんが小学校3~4年の頃?だったと思うが、一家で東京に移住したということだった。
ご家族のサポートあっての受賞なんだろうと思うと、胸が熱くなった。
最近こういった話はスポーツ選手でも多い。
小さい頃からご両親がフルサポート、教室までの送り迎えや栄養管理など、何から何まで全て親がやる。
今の有名選手は「親子二人三脚でした」という話を本当によく聞く。
もちろんこういう人たちと、普通の子供を一緒にしてはいけないと思う。
でも「せっかくここまでやったんだし、本人も好きでやってるし、まあちょっと上手くなったし」となると、親はどこまで引っ張っていいのか分からなくなる。
レベルは違うが私の娘もピアノを習っていた。
小学校5年生の後半になると本人が塾を優先すると言いだしたので、受験前は一旦中断して、中学入学後にまた始めた。
自分が小5で辞めて後悔していたので、娘には続けてほしいなという気持ちがあったというのもある。
結局娘はピアノが趣味の社会人になった。それはそれで良かったと思っている。
私はゲームはしないのだが、噂に聞く “どんどん課金していってしまう” という心理に、たぶん似てる。
ここまで課金したんだから、もうちょっとだけやってみようと。
そしてその間、決して安くはないお月謝に、お金が消えていく。
兄弟姉妹がいれば、2倍3倍になる。
1人だけ通わせるのは不公平だし、兄や姉がやっていることは、真似してやりたがるものだ。
スポーツでも芸術でも習い事は、一度始めて長く続ければ続けるほど、いつ辞めるかという出口戦略が必要なのだ。
小林愛実さんみたいに、誰の目にも天才!だったら、そんな必要はないんだけど。
もうそろそろかな、と親が思った時。
ここで子供本人の意思というものが、最大の問題だ。
子供本人が辞めたいのであれば、簡単。
子供は続けたい、親は辞めさせて勉強をさせたい時、さあ大変だ。
強権的な親なら、「お金を出しているのは親なんだから、言うことを聞け」というかもしれないが、それはお勧めできない。
勉強をするのも、習い事をするのも、辞めるのも、子供だ。
親が代わりにやってあげることはできない。
たまに、お母さんが学校に進学するんだろうか?と思うほど、本人を差し置いて受験に奮闘している方がいるが、それは逆効果だと思う。
習い事をやめて勉強に集中するのは、子供本人。
受験をして合格した学校に通うのも、子供本人。
本人の納得感無くして、成功はない。
嫌々ながらやったことが、成功する確率は低い。
子供が複数だと、一人一人にこのジレンマが起こる可能性があるのだから、親は本当に大変だ。
予算が立たない
このように子供には、予定外のお金がたくさんかかる。
日本の公的教育費は、GDP比世界ランキングで128位という低さ。OECD加盟国では36カ国中36位の最下位だ。
国は出してくれないから、教育費は家庭で用意しなきゃいけない。
その額、全て公立でも子供1人あたり1000万円弱とも言われている。
それに養育費(子供を育てるのにかかるお金)もかかる。
教育費と養育費で数千万円。
でも最終的に合計いくらかかるのかは、その時になってみないと分からない。
我が子とはいえ、どんな特性を持っているのかは、産まれて初めてわかる。
いや赤ちゃんの時はまだ分からない。
育っていく過程でだんだんわかってくるものだ。
つまり子育てというものは予算が立たない、ということ。
それなのに、「まあ大丈夫だろう」と、住宅ローンと教育費のダブル払いに突っ込んでいってしまうのは、やはり危険だろう。
教育費は親としてはケチりたくない。
無理してでも払ってしまう。
でも住宅ローンからは逃げられない。
そうなると、自分達の資産形成ができない。
下手したら、定年の前に赤字家計になってしまう。
人生100年時代、ここから長い。
私は教育費と養育費の目処が立つまでは、住宅ローンは組まない方が安全だと思う。
もちろん親が「私の人生の1番の夢が家を買うことであり、子供の教育費は絶対に出さない」というのであれば話は別だ。
でも一般的にはどっちも捨て難いという人がほとんどなので、人生をトータルで俯瞰してみたときのリスクを考えると、両方同時にというのは負担が大きい。
子供を育てるための家を買いたいという話はよく聞くが、子供と過ごせる期間はせいぜい20年くらい。
その後親の人生は長ければ50年くらいある。
子供が出ていった後の家は、広すぎて、古すぎて、住みにくい。
その時に売って小さな家を買おうと思っても、価値が低下していることが多い。
持ち家を勧める人は、賃貸だと自分のものにならないという。
でも自分のものになるということは、それにかかる税金や修繕費などのコストを自分で払うということだ。
もし火事になって近所に迷惑をかけたら、その責任も取らなければならない。
住宅ローンを滞納すれば、ブラックリストに載ってしまう。
つまりコストもリスクも背負いこむということだ。
子供を育てるということは、それだけで大きな責任を背負っている。
同時にマイホームの責任まで背負ったら、子供が巣立つ頃には家も自分達もボロボロになりかねない。
子供にかかる費用が総額いくらになるのかは、子供の将来の方向性が決まらないとと分からない。
習い事だけではなく、進路によってもかかる教育費は大きな差がある。
それらがはっきりするまでの子育て期間は、健全に家計を保つために賃貸で過ごし、マイホームに係るコストやリスクを避け、毎月積立で投資信託を購入して資産を作ることでリスクを最小限にする。
理論的には15年以上積み立てれば、ほぼ負けなしで資産形成できる。
子供が家を出たら、手元にある資産に応じて、家を買うなり、そのまま賃貸で過ごすなり、夫婦で話し合って決める。そのとき資産があれば何でも自由に選択できる。
人生100年時代、ひとつひとつ丁寧に進んでいってほしい。